税額控除
ページ番号1009314 更新日 2025年2月4日
所得控除が税率を乗じる前の所得金額から一定の金額を控除するものであるのに対し、税額控除は、税率を乗じて算出した税額から一定の金額を控除するもので、次のものがあります。
調整控除
平成19年に、所得税(国税)と市民税・府民税(地方税)の税率を変えることにより、国から地方への税金の移し替え(税源移譲)が行われました。
しかし、下表のとおり、市民税・府民税と所得税では、基礎控除や配偶者控除、扶養控除等の人的控除額が異なっており、同じ収入金額であっても、市民税・府民税の課税所得金額は所得税よりも多くなります。
そこで、これに起因する個々の納税者の負担増を調整するため、市民税・府民税額を減額する調整控除の制度が創設されました。
- 合計課税所得金額が200万円以下の人
- 「人的控除額の差の合計額」か「合計課税所得金額」のいずれか少ない額の5%を減額します。
- 合計課税所得金額が200万円超の人
-
{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5%の額を減額します。
ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円を減額します。
- ※合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額のことです。
- ※合計所得金額2,500万円超の場合については、調整控除は適用されません。

外国税額控除
国外に源泉のある所得について、その国の法令により所得税や市民税・府民税に相当する税を課されたとき、それに対してさらに本邦による市民税・府民税が課税されますと、国際間の二重課税になりますので、それを調整するために設けられた制度です。
つまり、外国税額控除とは、外国で課された所得税等の額を、所得税、府民税および市民税の控除限度額の範囲内において、まず所得税から控除し、所得税で控除しきれないときは府民税から控除し、それでも控除しきれないときは市民税から控除するものです。
なお、これらによっても控除しきれないときは、3年間の繰越控除が認められています。
配当控除
国内に本店を有する法人から受けた配当所得(申告分離課税を選択したものは除きます。)があるときは、配当支払前の法人所得について法人税が課税され、さらに、個人に対しても所得税と市民税・府民税が課税されるため、その二重課税を調整するために設けられた制度です。
配当控除の適用のある配当所得は、法人から受ける利益の配当、出資金に係る剰余金の分配、証券投資信託の収益の分配等に係るものであり、この配当所得の金額に、次の表に掲げる控除率を乗じて計算した金額を、所得割額を限度として控除することができます。
| 種類 | 課税所得金額: 1,000万円以下の部分 市民税 |
課税所得金額: 1,000万円以下の部分 府民税 |
課税所得金額: 1,000万円超の部分 市民税 |
課税所得金額: 1,000万円超の部分 府民税 |
|---|---|---|---|---|
| 利益の配当等 |
1.6% |
1.2% |
0.8% |
0.6% |
| 証券投資信託等: 外貨建等証券投資信託以外 |
0.8% |
0.6% |
0.4% |
0.3% |
| 証券投資信託等: 外貨建等証券投資信託 |
0.4% |
0.3% |
0.2% |
0.15% |
住宅借入金等特別税額控除
所得税で住宅ローン控除の適用がある人で、所得税から控除しきれなかった額を、翌年度の市民税・府民税から控除する制度です。
1 対象となる人
所得税で住宅ローン控除の適用を受けていて、平成21年から令和7年までの間に入居し、所得税から控除しきれない住宅ローン控除可能額がある人
2 対象とならない人
- 所得税が課税されていない人
- 所得税において、住宅ローン控除額を全額控除できた人
- 市民税・府民税が課税されていない人
3 控除額
次の1、2のいずれか少ない額が市民税・府民税の所得割額から控除されます。
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
2.所得税の課税総所得金額等の額の5%(上限97,500円)※
※ただし、次のいずれかに該当する場合は、所得税の課税総所得金額等の額の7%(上限136,500円)
・平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居し、消費税率8%または10%にて住宅を取得した場合
・注文住宅の場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日までに、分譲住宅等の場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約し、令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居した場合
4 控除の手続き
市町村への申告は不要です。
入居を開始した年は翌年に確定申告を、2年目以降は年末調整や確定申告をしてください。
なお、勤務先から配付される源泉徴収票や、確定申告書に次の項目の記載が必要となりますので、ご確認ください。
- 住宅借入金等特別控除(可能)額
- 居住開始年月日
寄附金税額控除
都道府県・市区町村や住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、住所地の都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金を支出した場合は、寄附金税額控除を受けることができます。
1 控除対象となる寄附金の範囲
(1) 都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税と市民税・府民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限があります。)。
例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養親族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と市民税・府民税から控除されます。
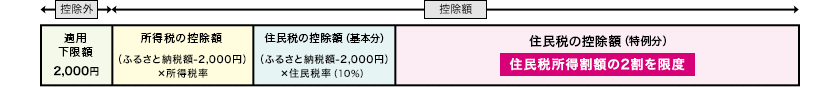
※地方税法等の一部を改正する法律の成立により、令和元年6月1日以降の寄附について総務大臣が以下の基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象と指定し、指定対象外の地方団体への寄附金については住民税の控除額(特例分)が控除の対象外となり、所得税の控除額および住民税の控除額(基本分)のみが控除の対象となります。
- 寄附金の募集を適正に実施する地方団体
- (1の地方団体で)返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体
- 返礼品の返礼割合を3割以下とすること
- 返礼品を地場産品とすること
ふるさと納税の詳細については、次のリンクをご参照ください。
また、ふるさと納税ワンストップ特例制度については次のリンクをご覧ください。
(2) 大阪府共同募金会または日本赤十字社大阪府支部に対する寄附金で、政令で定めるもの
なお、被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に支払った義援金は、(1)のふるさと納税としての取扱いとなります。
(3) 所得税法等に規定される寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として大阪府または吹田市の条例で定めるもの
現在、大阪府が条例により指定している団体については大阪府のホームページを参照してください。
吹田市が条例指定している寄附金については、各寄附先へご確認ください。
2 控除額
控除には基本分と特例分があり、ふるさと納税には特例分が加算されます。
(1) 基本分
{寄附金(総所得金額等の30%を限度)-2,000円}×税率(注)=税額控除額
(注) 税率について
- 吹田市が条例指定している寄附金の場合は、市民税6%
- 大阪府が条例指定している団体への寄附金の場合は、府民税4%
- ふるさと納税および大阪府共同募金会・日本赤十字社大阪府支部に対する寄附金の場合は、市民税6%、府民税4%の合計10%
(2) 特例分
(寄附金-2,000円)×下表の割合
ただし、市民税・府民税の所得割額の20%が限度となります。
| 課税総所得金額から人的控除額の差の合計を控除した金額 | 割合 |
|---|---|
| 0円以上~195万円以下 |
84.895% |
| 195万円超~330万円以下 |
79.79% |
| 330万円超~695万円以下 |
69.58% |
| 695万円超~900万円以下 |
66.517% |
| 900万円超~1,800万円以下 |
56.307% |
| 1,800万円超~4,000万円以下 |
49.16% |
| 4,000万円超 |
44.055% |
| 0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) |
90% |
| 0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有する場合) | 地方税法に定める割合 |
※割合の算出方法
割合=90%-{0~45%(所得税率)×1.021(復興特別所得税率)}
3 控除の手続き
(1)手続き
- 原則として、所得税の寄附金控除と市民税・府民税の寄附金税額控除の両方の控除を受けようとする人は、所轄税務署で所得税の確定申告が必要です。
なお、所得税の確定申告をしたときは、市民税・府民税の申告は不要です。 - 所得税の確定申告を行わない人は、市民税・府民税の申告をすることにより、寄附金税額控除を受けることができます。
*参考(外部サイト:地方税ポータルシステムへのリンク)
(2)ふるさと納税ワンストップ特例制度
- 確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の控除を受けられる制度です。
- 特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
- 特例の適用に関する申請書を提出したのち、住所に変更があった場合は、各ふるさと寄附金先団体へ変更届出書を提出する必要があります。
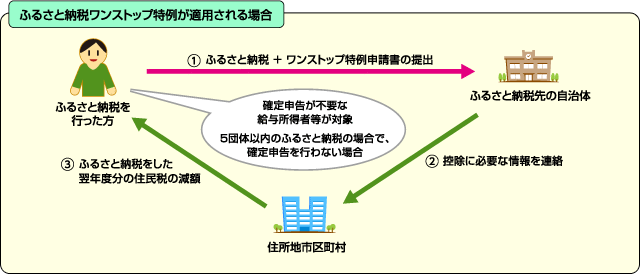
特例の適用に関する申請書・特例申請事項変更届出書のダウンロードは次のリンクをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
税務部 市民税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階 201,202,203番窓口)
電話番号:
【特別徴収・普通徴収の個人市民税】 050-1721-2523 ※自動応答
【軽自動車税・事業所税・諸税】 050-1721-4360 ※自動応答
【庶務・税証明】 050-1721-2235 ※自動応答
【法人市民税】050-1721-2523 ※自動応答
ファクス番号:06-6368-7344
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
