データヘルスの推進
ページ番号1018618
全国トップレベルにある本市の平均寿命・健康寿命の更なる延伸を目指し、北大阪健康医療都市(健都)に集積する健康医療関連企業や、国立循環器病研究センターをはじめとする研究機関との連携により、データヘルスの取組を推進していきます。
データヘルスで何が変わる?
国を中心に、健康・医療・介護の分野において、これまで別々に保存・保管されていた情報を、1か所に集約しようとする取組が進められています。それによって、皆さんの生活で、次のことができるようになります。
スマートフォンで健診等の情報を管理
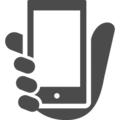
PHR※1(個人の健康診断結果や服薬歴等の健康等情報)を、スマホ等で一人ひとりが自分自身で生涯にわたって時系列的に管理・活用することができ、自身の健康管理や病気の予防などに役立てることができます。
医療・介護現場で患者情報を共有

地域の病院や診療所などをネットワークでつないで、患者情報等を共有し活用することができ、医療・介護現場で、過去の医療情報を確認したうえでサービスを提供することができるようになります。
ビッグデータから健康増進・病気の予防に繋げる

データを1か所に集約することで、健康医療に関するビッグデータを民間企業や研究者が利活用できます。また、得られた知見がICTなどを通じて発信されることで、自身の健康増進や病気の予防などに活用することができます。
※1 マンガで学ぶPHR
PHRの重要性について、具体的な活用方法を踏まえて、マンガの中でわかりやすく紹介しています。


※このマンガは、日本医療研究開発機構(AMED)の「医療・介護・健康データ利活用基盤高度化事業(医療高度化に資するPHRデータ流通基盤構築事業)」の成果物として、PHR普及推進協議会の協力のもと作成されたものです。
データヘルスの推進状況
健康医療情報の利活用
市が保有する健(検)診情報などの健康医療情報を、本人の同意を原則とした上で適正に利活用するため、市が目指す将来像などの基本的な考え方を示した方針を策定しています。
また、基本方針の下、本市の健康医療情報を外部提供するに当たり、統一した提供判断基準と手続を定め、適正かつ効率的な事務処理を促進するため、ガイドラインを策定しています。
健都におけるデータヘルスの推進
本市では、国循を中心に構築が進む国際級のバイオテクノロジー研究開発拠点(通称「共創の場」:文部科学省プロジェクト)に様々な健康医療情報を集約し、データ分析等を通じて、新たな予防策・治療法などの開発につなげていきます。
具体的には、生涯にわたる健康・医療情報の切れ目のない利活用をめざし、国循等と連携して以下の各プロジェクトを進めています。そこで得られた研究成果は、個人が使用するスマホ等を通じて還元します。
健康医療情報を活用した研究一覧
|
No |
研究名 |
研究期間 |
研究機関 |
活用データ |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
人工知能による小児期の心電図診断とスクリーニング |
2022~2025.3 |
国立循環器病研究センター |
年齢/性別/心電図所見/12誘導心電図波形 |
|
2 |
学童・思春期における高血圧等循環器疾患の診断法に関する縦断研究(吹田Offspring研究) | 2022.3~2051.3 | 国立循環器病研究センター | 乳幼児健診/学校健診/生活習慣病予防検診 |
|
3 |
都市部地域住民を対象とした心不全と認知症コホート研究(吹田研究NEXT) | 2021.7~2051.12 | 国立循環器病研究センター | 医療レセプト/介護保険/国保健診/健康長寿健診/生活習慣病予防健診/異動情報 |
|
4 |
縦断的な健康情報の分析等による子供の健康支援に関する研究 | 2021.6~2024.6 |
国立循環器病研究センター 大阪大学 |
乳幼児健診/学校健診/生活習慣病予防検診 |
|
5 |
吹田市健診受診者を対象とした心不全の予後因子に関する長期追跡研究 |
2020.10~2051.6 |
国立循環器病研究センター |
国保健診/健康長寿健診/生活習慣予防健診/30歳代健診 |
|
6 |
吹田研究 |
1989~2012.12 |
国立循環器病研究センター |
総合健診/氏名/住所/生年月日/性別/異動情報 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。
